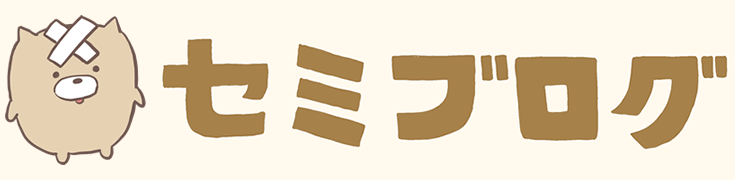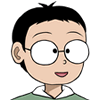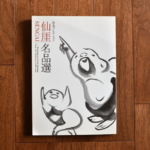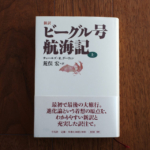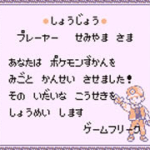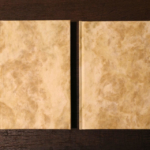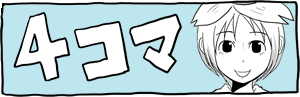村上春樹「雨天炎天」ギリシャ編 エンドレスに楽しめるスルメエッセイ
僕はそこそこ本は読む方だけど、同じ本を読み返す事はほとんどない。
高い本を買っても一度しか読まずにブックオフって事が多くコスパが非常に悪いので、値段が高く、それでいて一度は読みたい本は図書館で借りるようにしている。
そんな僕にとって、例外的に何度も読み返しているのが、村上春樹の旅エッセイ。
「遠い太鼓」「辺境・近境」など色々あるが、特に多くリピートしているのが「雨天炎天」。

この本、サブタイトルの「ギリシャ・トルコ辺境紀行」からも分かるように、前半はギリシャ正教の聖地・アトス半島への旅。後半はトルコ一周旅行について書かれている。
今回は、前半のギリシャ編について書いてみようと思う。
基本的には冷静で、客観的なんだけど、しっかり届く。そんな感じがする。
過度にウェットだったり、熱かったり、しつこくない。それが何度も読める理由の一つだと思う。
宗教に身をささげたストイックな、本気の男たちが暮らす、宗教に淡泊な日本人にとって完全なる異界。
作中で春樹も書いているように、自分の人生、生き方に対する確信の強さは、不安定な現代日本に暮らす我々とは全く異なっている。
その強さ、揺るぎの無さに惹きつけられる。
・アトスへの直行便が出ている唯一の街「ウラノポリ」着
・ウラノポリからアトスへ船で移動
・海岸線に沿って続く道を、各所にある修道院を拠点に進む。
・旅程いっぱい道を進み、ウラノポリに戻る
ウラノポリは、「聖地」アトスに対する俗世間の象徴として描かれる。
春樹が言うところの「どこにでもあるギリシャの小銭集金型ビーチ・リゾート」。
アトスへ着いてからは、半島内に存在する20の修道院を一つ一つ訪れ、食料を貰ったり、宿坊のように泊めてもらいながら、よりワイルドな地域へと足を進めていく。
食事の美味しさ、人の良さなどはピンキリで、青カビがびっしり生えたパンを出される時もあるし、修道院で栽培した新鮮な野菜を惜しげもなく分けてくれる所もある。
カラカル修道院では、真夜中に蝋燭の明かりに照らされて詠唱をする修道僧たちを、春樹が目撃する。
ギリシャ正教という宗教の凄みを感じさせる、とりわけ印象的なシーンだ。
旅に出ると、日頃のルーチン化した生活と切り離された意外性、新鮮な体験が出来る反面、予定通り進まなかったり、トラブルに遭遇したりする。
このエッセイでも唖然とするような価値観の相違や、日本では考えられないようなトラブルに巻き込まれ、四苦八苦する春樹を通して、旅のいいところ、きついところ、ひっくるめて追体験できる。
春樹も「逆に言えば、物事がとんとんとんと上手く運ばないのが旅である。上手く運ばないからこそ、我々はいろんな面白いもの・不思議なもの・唖然とするようなものに巡り合えるのである。そして、だからこそ我々は旅をするのである」と書いている。
・ルクミという甘いゼリー菓子
・ウゾーというギリシャでよく飲まれる強い酒の水割り
・砂糖のたっぷり入ったギリシャ・コーヒー
この3点セットがもれなく出てくる。
甘いものが苦手な春樹は、最初はルクミなどは甘すぎて一口しか食べられないのだが、旅が佳境になるにつれ疲労が溜まり、体が糖分を欲するようになってきて、出されたルクミはすべて平らげるようになる。
最終的には「はやく次の修道院に着いてルクミを食べたい」とまで思うようになる。
このルクミに対する変化が、旅の道のりの険しさと比例しているのが面白い。
高い本を買っても一度しか読まずにブックオフって事が多くコスパが非常に悪いので、値段が高く、それでいて一度は読みたい本は図書館で借りるようにしている。
そんな僕にとって、例外的に何度も読み返しているのが、村上春樹の旅エッセイ。
「遠い太鼓」「辺境・近境」など色々あるが、特に多くリピートしているのが「雨天炎天」。
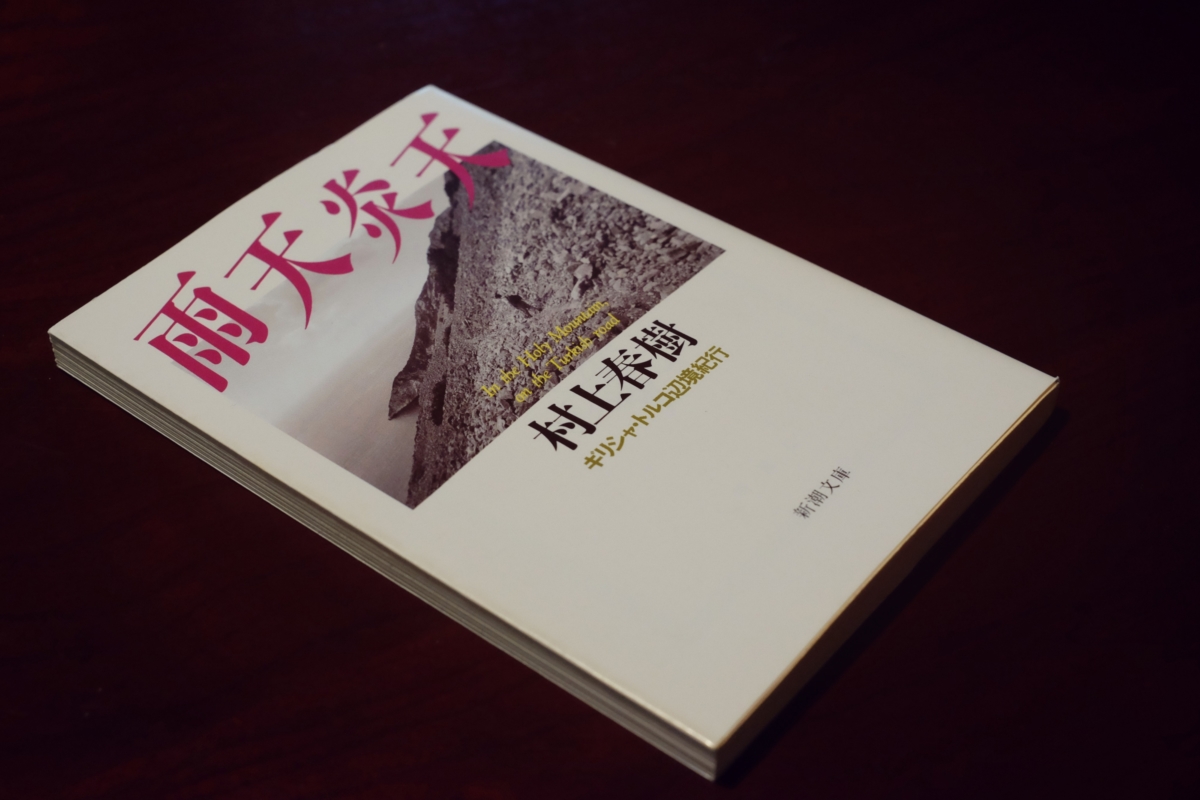
この本、サブタイトルの「ギリシャ・トルコ辺境紀行」からも分かるように、前半はギリシャ正教の聖地・アトス半島への旅。後半はトルコ一周旅行について書かれている。
今回は、前半のギリシャ編について書いてみようと思う。
村上春樹の文体のちょうど良さ
全編を通して、というか村上春樹の他の作品にも言える事だけど、事物を描写する時の春樹の(と呼ばせてもらおう)文体、ほんとに絶妙だなと思う。基本的には冷静で、客観的なんだけど、しっかり届く。そんな感じがする。
過度にウェットだったり、熱かったり、しつこくない。それが何度も読める理由の一つだと思う。
アトス半島そのものの魅力
このエッセイで春樹が旅するアトス半島は、ギリシャという国の中にあって完全な自治を認められたギリシャ正教の聖地であり、女人禁制の地だ。宗教に身をささげたストイックな、本気の男たちが暮らす、宗教に淡泊な日本人にとって完全なる異界。
作中で春樹も書いているように、自分の人生、生き方に対する確信の強さは、不安定な現代日本に暮らす我々とは全く異なっている。
その強さ、揺るぎの無さに惹きつけられる。
旅の道のり
このアトス旅行記で春樹が辿った道のりは、非常にシンプルだ。・アトスへの直行便が出ている唯一の街「ウラノポリ」着
・ウラノポリからアトスへ船で移動
・海岸線に沿って続く道を、各所にある修道院を拠点に進む。
・旅程いっぱい道を進み、ウラノポリに戻る
ウラノポリは、「聖地」アトスに対する俗世間の象徴として描かれる。
春樹が言うところの「どこにでもあるギリシャの小銭集金型ビーチ・リゾート」。
アトスへ着いてからは、半島内に存在する20の修道院を一つ一つ訪れ、食料を貰ったり、宿坊のように泊めてもらいながら、よりワイルドな地域へと足を進めていく。
個性豊かな修道院
各修道院では、無料で食事をしたり、泊めてもらう事ができる。食事の美味しさ、人の良さなどはピンキリで、青カビがびっしり生えたパンを出される時もあるし、修道院で栽培した新鮮な野菜を惜しげもなく分けてくれる所もある。
カラカル修道院では、真夜中に蝋燭の明かりに照らされて詠唱をする修道僧たちを、春樹が目撃する。
ギリシャ正教という宗教の凄みを感じさせる、とりわけ印象的なシーンだ。
僕らが旅に出る理由
「雨天炎天」は短いエッセイだが、旅の醍醐味みたいなものが凝縮されている。旅に出ると、日頃のルーチン化した生活と切り離された意外性、新鮮な体験が出来る反面、予定通り進まなかったり、トラブルに遭遇したりする。
このエッセイでも唖然とするような価値観の相違や、日本では考えられないようなトラブルに巻き込まれ、四苦八苦する春樹を通して、旅のいいところ、きついところ、ひっくるめて追体験できる。
春樹も「逆に言えば、物事がとんとんとんと上手く運ばないのが旅である。上手く運ばないからこそ、我々はいろんな面白いもの・不思議なもの・唖然とするようなものに巡り合えるのである。そして、だからこそ我々は旅をするのである」と書いている。
ルクミと春樹
アトスの修道院では、辿り着いた旅人をもてなすための3点セットというのがあって、・ルクミという甘いゼリー菓子
・ウゾーというギリシャでよく飲まれる強い酒の水割り
・砂糖のたっぷり入ったギリシャ・コーヒー
この3点セットがもれなく出てくる。
甘いものが苦手な春樹は、最初はルクミなどは甘すぎて一口しか食べられないのだが、旅が佳境になるにつれ疲労が溜まり、体が糖分を欲するようになってきて、出されたルクミはすべて平らげるようになる。
最終的には「はやく次の修道院に着いてルクミを食べたい」とまで思うようになる。
このルクミに対する変化が、旅の道のりの険しさと比例しているのが面白い。
created by Rinker
¥515
(2026/02/20 02:00:32時点 Amazon調べ-詳細)